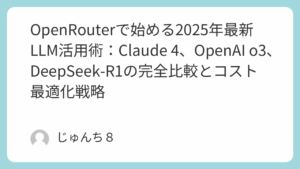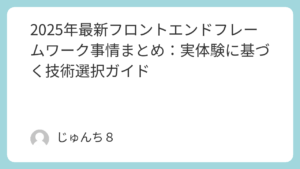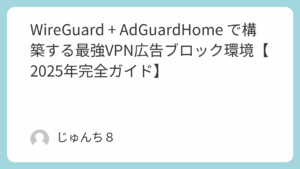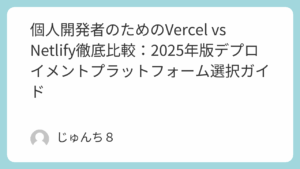目次
1. [なぜシンセポップにハマったのか](#なぜシンセポップにハマったのか)
2. [フェリシア楽曲で使っている制作手法](#フェリシア楽曲で使っている制作手法)
3. [実際の楽曲制作プロセス](#実際の楽曲制作プロセス)
4. [よく使うコード進行とシンセ設定](#よく使うコード進行とシンセ設定)
5. [制作で気をつけていること](#制作で気をつけていること)
6. [今後チャレンジしたいこと](#今後チャレンジしたいこと)
—
なぜシンセポップにハマったのか
フェリシア名義で楽曲制作を始めたとき、最初は「どんなサウンドにしよう?」と悩んでいました。
そんな時に出会ったのがシンセポップの世界。80年代のレトロなシンセサウンドと現代的なポップスの組み合わせに、一瞬で心を奪われました✨
シンセポップの魅力
- 🎹 カラフルなシンセサウンド: 聴いているだけで心が弾む
- 💫 ノスタルジックな雰囲気: 懐かしくて新しい不思議な感覚
- 🎵 キャッチーなメロディ: 一度聴いたら頭から離れない
- 🌈 自由度の高さ: ポップからアンビエントまで幅広い表現
> 「この音楽で聴く人を笑顔にしたい!」
そんな想いから、J-POP × シンセポップの楽曲制作をスタートしました。
フェリシア楽曲で使っている制作手法
—
—
実際にリリースした楽曲を例に、制作手法を紹介します。
「エターナル・ラブレイド」での学び
#### 基本構成
Intro (8小節) → Verse (16小節) → Pre-Chorus (8小節)
→ Chorus (16小節) → Verse2 → Pre-Chorus → Chorus
→ Bridge (8小節) → Last Chorus → Outro#### 音色選び
「Jump up!」でのコラボ制作
Manakarenさんとのコラボ楽曲では、エネルギッシュなダンスポップを意識:
#### ポイント
実際の楽曲制作プロセス
Step 1: コンセプト決め
まず「どんな気持ちを伝えたいか」を明確にします。
例:「恋のシグナル」の場合
Step 2: コード進行作り
シンセポップでよく使うコード進行:
#### 王道パターン
Key: C major
C - Am - F - G (カノン進行)
C - G - Am - F (小室進行)
Am - F - C - G (切ない系)#### 少し変化をつけたい時
C - Am - Dm - G (サブドミナントマイナー)
C - Em - F - G (明るくて爽やか)Step 3: メロディ制作
#### 意識していること
Step 4: アレンジ・音色作り
#### シンセサウンドの作り方
基本的なシンセパッド:
オシレーター: Saw wave + Sub oscillator
フィルター: Low-pass filter (Cutoff: 70-80%)
エンベロープ: ゆっくりしたAttack, 長めのRelease
エフェクト: Reverb + Chorus よく使うコード進行とシンセ設定
感情別コード進行
#### 明るく楽しい曲
C - F - G - Am → F - G - C「Jump up!」「GET READY STAR」で使用
#### 切なくロマンチック
Am - F - C - G → Dm - G - C「エターナル・ラブレイド」「ふたりのキズナ」で使用
#### 神秘的・幻想的
Am - Dm - G - C → F - Bb - Gm - C「Dive into my magic」で使用
よく使うシンセ音色設定
#### リードシンセ(メロディ用)
#### パッドシンセ(和音用)
#### ベースシンセ
制作で気をつけていること
音楽面での工夫
#### 1. 聴きやすさを最優先
#### 2. 日本語の美しさを活かす
#### 3. エモーショナルな表現
技術面での注意点
#### ミックス・マスタリング
#### 音楽的な理論
今後チャレンジしたいこと
短期的な目標
#### 音楽制作スキル向上
#### 楽曲の幅を広げる
長期的な展望
#### アーティストとしての成長
#### 技術的な挑戦
音楽で伝えたいメッセージ
> 「毎日の生活に彩りと温かさをお届けしたい」
これからも、聴いてくださる皆さんの心に寄り添える音楽を作り続けていきたいと思います。
フェリシアの楽曲が、あなたの大切な瞬間に寄り添えたら嬉しいです💕
まとめ
制作を通じて学んだこと
#### 技術的な発見
#### 創作活動の喜び
これから楽曲制作を始める方へ
もし「自分も音楽を作ってみたい」と思ったら:
1. 好きな音楽を分析: まずはたくさん聴いて、何が好きかを知る
2. 簡単なツールから: DAWソフトの無料版やアプリから始める
3. 理論は後から: 最初は感覚で、慣れてから理論を学ぶ
4. 完璧を求めない: 最初の作品は練習だと思って気楽に
5. 楽しむことが一番: 音楽制作は楽しんでこそ良いものができる
音楽には正解がありません。あなたらしい表現を見つけて、ぜひ音楽制作を楽しんでください🎵
—
関連リンク
📌 この記事は2025年8月時点での制作経験に基づいています。