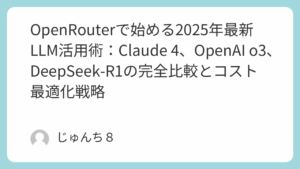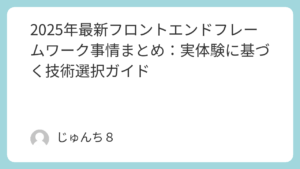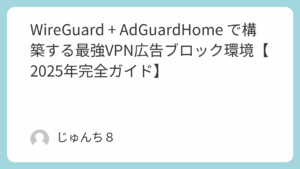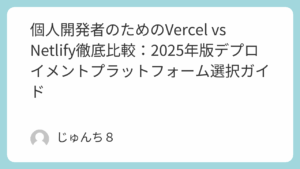目次
1. [個人音楽配信を始めたきっかけ](#個人音楽配信を始めたきっかけ)
2. [実際に試したマーケティング手法](#実際に試したマーケティング手法)
3. [SNS活用の現実と課題](#sns活用の現実と課題)
4. [音楽配信プラットフォーム戦略](#音楽配信プラットフォーム戦略)
5. [失敗から学んだこと](#失敗から学んだこと)
6. [今後の展望と改善点](#今後の展望と改善点)
—
個人音楽配信を始めたきっかけ
じゅんち8とフェリシアの2つの名義で音楽活動を始めて、早速直面したのが「どうやって音楽を聴いてもらうか」という問題でした。
最初の現実
楽曲をリリースした直後:
- 再生数: 数十回(ほぼ身内😅)
- フォロワー: ゼロからスタート
- 認知度: 皆無
- 毎日10万曲以上がSpotifyにアップロード
- 膨大な楽曲の中で埋もれてしまう
- 偶然の発見だけでは限界がある
- プロフィール最適化: アーティスト写真・バイオ充実
- プレイリスト申請: Spotify編集部へのピッチ
- アーティストピック: 定期的な投稿でファンとのコミュニケーション
> 「良い音楽を作れば自然と聴いてもらえる」
そんな甘い考えは一瞬で崩れ去りました💦
なぜマーケティングが必要なのか
音楽業界の現実:
だからこそ、戦略的にアプローチする必要があると実感しました。
実際に試したマーケティング手法
1. 音楽配信プラットフォーム攻略
#### Spotifyでの取り組み
#### 実際の結果
初回リリース(エターナル・ラブレイド):
1週間目: 127再生
1ヶ月目: 1,240再生
3ヶ月目: 3,850再生 #### 学んだこと
2. SoundOnでの展開
#### 取り組み内容
#### 特徴的だった結果
3. ウェブサイト・ブログ活用
#### じゅんち8ポータルサイト構築
#### コンテンツマーケティング
SNS活用の現実と課題
試したプラットフォーム
#### Twitter(X)
やったこと:
結果:
#### Instagram
やったこと:
課題:
#### TikTok
試したこと:
現実:
SNSマーケティングの教訓
#### 成功要因
#### 失敗から学んだこと
音楽配信プラットフォーム戦略
プラットフォーム別の特徴と戦略
#### Spotify
特徴:
戦略:
#### Apple Music
特徴:
戦略:
#### YouTube Music
特徴:
戦略:
実際の配信戦略
#### リリーススケジュール
月別リリース計画:
第1週: メインリリース(新曲)
第3週: リミックス/アコースティック版
月末: 次回作の予告・ティーザー #### メタデータ最適化
失敗から学んだこと
大きな失敗談
#### 1. 「バズれば成功」思考
何をやったか:
結果:
学び:
> 「持続可能性」と「音楽の質」が最重要
#### 2. プラットフォーム依存
何をやったか:
結果:
学び:
> 「マルチプラットフォーム戦略」と「直接的なファンベース構築」の重要性
#### 3. 数字至上主義
何をやったか:
結果:
学び:
> 「質的な関係性」と「音楽への情熱」を最優先に
現在の方針転換
#### 音楽ファースト
#### オーガニック成長
#### 健全な距離感
今後の展望と改善点
短期的な改善計画(3-6ヶ月)
#### コンテンツ戦略
#### 技術的改善
長期的なビジョン(1-2年)
#### アーティストとしての成長
#### コミュニティ構築
#### 持続可能な活動
音楽活動で大切にしたい価値観
#### 音楽への純粋な愛
> 「数字や成功に惑わされず、音楽そのものを愛し続ける」
#### ファンとの真摯な関係
> 「表面的な宣伝ではなく、心から音楽を共有できる関係を築く」
#### 持続可能な創作活動
> 「一発屋ではなく、長く愛される音楽を作り続ける」
まとめ
マーケティングを通じて学んだ最重要ポイント
1. 音楽の質が最優先: どんなマーケティングも、良い音楽なしには成り立たない
2. 継続性が力: 短期的な成果より、長期的な積み重ねが重要
3. 真摯な関係性: ファンとの本物のつながりが最大の資産
4. バランス感覚: マーケティングと音楽制作の適切なバランス
5. 楽しむ気持ち: 最終的には、音楽活動を楽しめることが一番大切
これから音楽活動を始める方へのアドバイス
#### 最初に大切なこと
#### 避けた方が良いこと
#### 長期的に意識すること
音楽活動は marathon であって sprint ではありません。
焦らず、楽しみながら、自分らしい音楽を作り続けることが、結果的に最良の「マーケティング」になるのだと思います🎵
—
関連リンク
📌 この記事は2025年8月時点での実体験に基づいています。